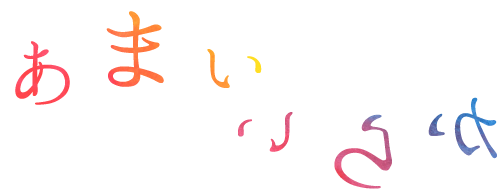
気が付いていないわけじゃない。たとえば。いまわたしの目の前に座っている、おとぎ話の王子様みたいなこのひとと、こんな風にふたりきりで向き合いたい女子なんて、この学校にはごまんといるんだってこと。そんな彼が、自分に向けるまなざしの温度について。
「ねえ。今日、女子はマフィンつくったんでしょ?」
「……よくご存知で」
「何言ってるの、みんな知ってるよ」
「どうせ不二のことだから、山程もらったんじゃない?」
「へぇ…また随分いやな言い方するね。かわいくないな」
そりゃどうも。と投げやりに返したわたしを、不二は貼り付けたような笑顔で見つめていた。同じグループで調理していた子たちが、わざわざ持ち寄った色とりどりのラッピングで、一様に焼き上がる何の変哲もないマフィンに個性をつけようとやっきになっていた姿を思い出す。あの子たちのうちの少なくとも半数は、今日は不二くん受け取ってくれるかなと叶わぬ期待に浮足立っていたはずだ。
いつのまにか頬杖をついて窓の外に視線を移している彼を見て、あらためて思う。色素の薄い髪、テニス部にしては白い肌、中性的な顔立ち。飾り気のない詰襟が、彼のとびきり秀でた容姿をより一層際立てていた。こんなにもうつくしい男の子に好きになられて、応えないどころか嬉しくもないなんてまったくどうかしている。
開けっ放しにされていた窓から吹き込む、冬のはじめの冷たい風が、不二の髪を僅かにさらって抜けていった。
「なに見てるの?」
「…べつに。相変わらずきれいな顔だなって」
「そう。それは、ありがとうって言えばいいのかな?」
不躾なわたしのまなざしに呆れるでも怒るでもなく、微かな笑みを浮かべてそう言った不二に返す言葉が見つからなくなって、思わず視線を足元へと落とした。ほんの僅か残った罪悪感を刺激するように、動かした視界の端、清楚なベージュの包みを見つけてしまう。それは、一ミリの隙もないくらい丁寧に、彼の好みを反映していた。
定期的にやってくる調理実習後の差入れは、不二のような人気者ではどうにも収拾がつかなくなる。それ故に、彼はいつも例外なくすべてを断っていたはずだ。だから小さな紙袋に収められたそれは、少なからずわたしの心を掻いた。そんな痛みを感じる資格、わたしにはこれっぽっちもないというのに。
「食べてくれなくてもいいからって言われて、断りきれなかったんだよね」
あんまり真っ直ぐな目で言うもんだからさ。わたしの視線に目ざとく気がついて、不二がひとりごとのようにそう呟いた。どうしても好きってことだけ伝えたいなんて言われたらね、と諦観の滲む笑みを零されて、こちらが泣きそうになるなんて筋違いもいいところだ。外面さえも完璧なこのひとが、自分にだけ見せてくる気安さ。その意味をとうの昔に理解しながら、わたしはずっとそれに甘えてきた。
「は?英二に渡さなかったの」
それだから不二はこうして時々、答え合わせの必要もないような問いかけでわたしをちくりと刺してくる。もちろん、そのくらいの反撃なんてあって然るべきの振る舞いをわたしはしている。それでも、机にかけたスクールバッグから覗く透明のビニールをちらりと見れば、どうしたって心は軋む。不二が投げかけた意地の悪い質問に、「あげるわけないじゃん」と身勝手な悪態を返した。
「だって英二は、ぜったいに受け取るし、ぜったいに食べるから」
そう。彼はたとえその贈り物が誰からだって、おんなじ温度で「ありがと〜」と言えてしまうひとだ。どんなに仲の良い友人だって、ろくに話したことのないただのクラスメイトだって、皆みんなおんなしだ。ただひとり、あの子だけを除いては。
そしてわたしは彼の、そういうところがどうしようもなく好きで、どうしようもなく、大嫌いだった。どこまでもまっすぐな英二を好きになればなるほど、わたしの気持ちはぐちゃぐちゃに捩れて、見るに堪えない代物へと成り下がる。
「だいたい、一方的に好意を寄せてる相手がつくったものなんて気持ち悪くない?」
だから正直、食べて欲しくもないんだよね。そうやって自分を卑下するフリで、不二の机にかかる紙袋の中身までもわざわざ踏みにじる。散々こじらせたわたしの英二への想いはもはや、どこまでも最低でどこまでも下劣な、救いようのない好意になっていた。
「じゃあ、それはいらないんだ」
不二が、視線の斜め下、わたしの机の横を指差して微笑んだ。「いらないなら、僕にくれない?」と甘く笑うその顔は、女子の心をもれなく攫ってしまうような、完璧なキラースマイルだった。
「甘いの苦手なくせに」
「まあ、世の中には例外ってものがあるからね」
「もしかして、毒が入ってるかもよ」
好きなひとを独り占めするための、不浄な毒が。
渋々手渡したリボンを結んだだけのラッピングを受け取りながら、はじめて不二が眉をしかめた。三年塗り重ねた醜い想いをもってしても、息の根をとめるほどの毒にはなれない。そんなことはわたしも不二も痛いほどに解っている。お行儀よく結われた真っ赤なリボンを、乱雑に解いてぐしゃりと握った不二が、さざ波のような笑みを浮かべてわたしを見つめた。
「キミってほんとうに、僕を傷つける天才だよね」
取り出したマフィンを一口齧って、「まあこれで死ねるなら本望かもね」とごちる不二を、言いようのない優越をもって眺めていた。こうやっていつも、わたしはかわいそうな自分のことを、たいせつに守っている。だって不二が王子様である限り、わたしは決して、町娘Aになることはないのだから。
自分の物語をきちんと終わらせる勇気もないくせに、バッドエンドのないおとぎ話にいつまでも都合よく浸かり続けている。叶うことのないこの醜い気持ちを、大事にだいじに、抱えたまま。