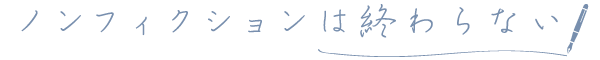
人もまばらな放課後の中庭。歩き慣れたテニスコートへと向かう道のり。時折通り過ぎる、後輩なのか同級生なのか、とにかく人という人の視線が痛い。それもそのはず、わたしの姿はどこからどう見ても、もはやとち狂っているとしか思えなかった。頭のてっぺんからつま先まで、どこから汲んだのかもわからないバケツの水でぐっしょりと濡らされてしまっているのだから。
そこを、偶然というにはなんとも計ったようなタイミングで通りがかった幸村がこちらを見とめ、一瞬状況を把握しようと思案する顔を浮かべてみせる。その後、取ってつけたように訝し気な表情を浮かべた彼はこう言いはなった。
「何してるの?水浴び?」
「…あんたにはそうみえるわけ?」
正直、びしょ濡れになりながら一番に頭に浮かんできたのは、いまどきこんな一昔前の少女漫画みたいなことするやついる?というとても客観的なそれだった。寒いだとか、冷たいだとか、悲しいとか悔しいとか、そういう感覚も感情も何もかもぜんぶすっとばして、わたしはただひたすらに呆れ果てていた。幸村くんに媚売ってんじゃねーよ!と言い捨てて走り去ったあの子たちに。この惨劇の要因となってしまっている人気者の幸村に。そして何より、甘んじてこんな事態を受けとめてしまった自分自身に。バケツの水くらい避けられたでしょ?何なら、そうなる前に逃げられたでしょ?そもそも、あんなあからさまに不穏な呼び出し、どうしていまさら安直に従ってしまったの?いらぬ考えが頭のなかを巡る。
不可思議なものでも見るような目で近づいてきた幸村は、訝し気な顔はそのままに、背負っていたラケットバッグからまっさらなタオルを一枚取り出した。
「まあとりあえず拭いたら?これ使いなよ」
「……ありがと」
お前が素直だとなんか怖いなあ、などと言って微笑む幸村にわたしは思う。何言ってんの?怖いのはあんただよ。誰がどう見ても普通じゃないこの状況にいながら、平然と目の前で微笑むこの男を見てわたしは、先日自分の身に起きたとんでもない出来事を思い返していた。
あれは、代替わり後の引継ぎも大方終え、ほとんどないオフの日を狙って部室に残していた荷物を片付けていた放課後。毎日の部活がないことにも慣れ、指導という名目で度々練習に顔を出す(赤也くらいしか喜ばない)目の上のたんこぶ状態な彼らが、年明けから高等部の練習に参加すると柳に聞かされた日。選手たちはたいへんだなあなんて、呑気に考えていたときだった。唐突に部室のドアが開き、いきなり部室に入ってきた幸村が「」とおよそ二年ぶりにわたしを名前で呼んだ。突然のことに面食らったわたしを正面に見据え、なんと二言目に幸村は「俺、お前のことが好きなんだ」と言いはなったのである。あまりにも脈絡のない展開と、予想もしない一言に、驚きすぎて返す言葉など出てくるわけもなく。茫然と幸村を見つめ続けるわたしに、彼は真面目な顔でこう続けた。だから、と。
「これからも、そばで見ていて欲しいんだ」
おそらくいままでにないくらいのとんでもない間抜け面をしていたであろうわたしに、一度からりとした笑顔を向け、「じゃあ、そういうことだから」と言ってまるで何事もなかったかのように幸村はさっさと帰っていってしまった。取り残されたわたしは、どうしていいのかもわからず、ひとり部室で立ち尽くしていた。好き?幸村がわたしを?まったくもって意味がわからなくて、一年生の秋に当時の三年生が引退してからというもの、いつもわたしのことをマネージャーと呼んでいた幸村にひさしぶりに呼ばれた自分の名前を、ただひたすらに反芻していた。
ひゅう、と冷たい風が吹き抜けて、思わず身震いしたわたしに幸村がちいさくため息をつく。
「まったく、仕方ないなぁ。これ貸してやるから」
「いやでも、それじゃ幸村が、」
寒いでしょ、と言いかけたわたしを視線で制して、幸村は見慣れた芥子色のジャージを脱いだ。寒空の下あらわになった彼の腕が、春先に病室で見たそれとはまったく違っていることにあらためて気づかされ、それまで心のなかでぐるぐると巡っていたものがまるで洪水みたいに急激に溢れだしてくる。俯いてしまったわたしを脱いだジャージで包むようにしてから、幸村はあきれたように笑った。
「なんだ、泣いてるの?これくらいのことで泣くなよ」
ほんとに世話がやけるなあ、うちのマネージャーは。
その聞き慣れた呼称がからだのなかをぐるりとめぐる。あんたたちに世話をやいたことはあっても、やいてもらったことなんかひとつもないと言い返してやりたかったけど、そんなことを声にすると余計に泣けてきてしまいそうだったのでやめた。
彼らと駆け抜けた夏をおもえば、こんな仕打ちはかすり傷にもならないくらい些末なことだ。
永遠にも感じられた夏を戦い抜き、彼らは新たな季節を見据え歩き出した。最後までマネージャーをつとめあげたわたしは、学校一人気の部の仲間に好きだと告げられた。これが少年漫画でも少女漫画でも、めでたしめでたし、トゥビーコンティニュー、彼らの輝かしい未来に乞うご期待!となるのだろう。
けれども、わたしたちの日常はこれからもずっとずっと続いていく。テスト前に後輩に泣きつかれたり、久しぶりに会う高等部の先輩にしごかれたり、やっかむクラスメイトに水をぶっかけられたりしながら。
はたして、この気持ちは恋と呼べるのだろうか。そもそも、わたしは彼に好きだと言われただけで、恋人になってほしいなどと言われたわけでもなかった。それでもいまわたしは、「とりあえず部室借りて着替えたら?」と、まったく仕方がないといった風でわたしの手を引くこの男の行く先を、これからも、まだまだずっと、自分のこの目で見届けてゆきたいと願ってやまない。
そして、前を歩く彼の背中がことのほか広いことや、繋がれたマメだらけの掌があたたかいことこそが、わたしのこれからの道のりを支えてくれるに違いないと、いまなら自信をもっていえる気がした。