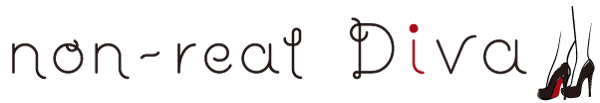
※仁王姉の設定を捏造しています。
うしろ姿で気づくのは恋、とはよく言ったものだ。
二十三時の住宅街、ひと気のないコンビニからの帰り道。目の前を歩く、心なしか覚束ない様子の足元を見れば、外灯のつたないあかりに照らされて浮かぶ真紅の靴底。それだけでもう、その存在に気が付けてしまうのだ。これを恋と呼ばずして、いったい何と呼べばいい?
振り向かれてしまわないようにと、しずかに足を速めて近づけば、おんなのひとの汗と雑多な煙草のにおいの中に、あまいオードトワレがうっすら香った。そんなことでいともかんたんに気持ちがうごく。
「お、べっぴんさんがおる」
ゆっくりと追い越して、彼女の正面を振り返れば、驚いたように見開かれた目の縁はほんのりあかい。一拍おいて「まーくんだあ」とうわずった声で俺を呼び、さんは破顔した。あいかわらず気にくわないその幼い呼び名だったけれど、それを唱える唇の艶めかしさと、はじめて見る警戒心のかけらもない笑顔とのくいちがいに、胸は軽率に高鳴った。彼女の身体から微かに香るアルコールは、中学生という身分では本来ならば共有し得ない、背徳と甘美の香りだ。かみさま、この偶然をあたえてくれてありがとう。
それなのに、彼女は俺の気持ちを操縦する天才だった。不意に許された急上昇、束の間の喜びの後、即急降下。
「中学生がこんな時間に出歩いちゃだめだぞお」
ふふ、という酔いのまわった笑い声が、甘くふくらんだ気持ちをあっさりと萎ませる。艶めかしく腰を折って、隣からこちらを覗き込む彼女が湛える無意識の嬌態が途端に憎らしく思えた。拗ねた顔を取り繕い「姉貴のパシリなんやけど」とコンビニスイーツの入った袋を掲げれば、彼女は少し困ったように目尻を下げて見せる。「あの子はほんと弟遣い荒いなあ」と笑って、えらいねとまるでこどもにするみたいに俺の頭を撫でた。こんなこども扱いなんてちっともされたくなんかないのに、その指先が与えるあまい刺激でどうしようもなく胸が擦り切れそうになる。このひとといると、あたまんなかが忙しなくてたまらない。こども扱いすんな。もっと撫でて。正反対の願いがぶつかりあう。
姉が初めて彼女をうちに連れてきたとき、俺はまだぴかぴかの中学一年生だった。姉と同じ美容学校に通うさんは、小学生に毛が生えたくらいのガキだった当時の俺からすると、とんでもない高嶺の花に思えたものだ。明るい髪に、派手すぎない品のあるメイク。顔や服装の華やかさとは裏腹に、爪の先はいつもカラー剤で染まっていて、それだけが唯一彼女の真面目さを教えていた。
中学二年の秋、横浜の美容室に就職したさんを生意気にも自宅へ呼び出して、俺は初めて髪を染めた。練習台になるという口実は、今思えばなかなかに無理があったけれど、なぜだか姉をとても慕っているさんはその弟の俺のお願いを二つ返事で了承してくれたのだった。就職後も彼女がそう遠くない近所に住んでいるのをいいことに、俺は髪を染める度に彼女を我が家に呼んでいた。あるとき、さんがなんの気まぐれか「新商品のカラー剤お店でもらったからうちで試さない?」と提案してきたときには、それまでにまるで経験したこともない高揚感で、いまにも胸が張り裂けそうになったのを、昨日のことのように思い出せる。
「やっぱりいいね、きれいなプラチナ」
「さんにもろたシャンプー、ちゃんと毎日つこうとるもん」
「ん、えらい。あ、でも生え際、けっこう黒くなってるな」
自身が染め上げた髪を、彼女の指が探るようにかきわけて、その爪先がやわく地肌を掠る。頭ならば何度だって触れられたことはあるのに、こんな風に夜道で肩を並べて歩いているという非日常が、その心地よさとこそばゆさとをいやに増長させた。
「またさんに染めてもらわんとじゃな」
「んー?いいけど、たまにはお姉ちゃんにやってもらわなくていいの?」
「だめ。…アイツにやらせると、ぜーったいうまいことならん」
「ええ?そうかなあ。あの子のほうがうまいと思うけど」
でもいいよ、やったげる。なんて、駄々っ子を宥めるみたいに笑われてしまえば、「俺があなたにやってもらいたいだけ」などという、周到に用意していた色付きのわがままはとても言えなくなってしまう。こうやってこども扱いされるからこそ素直にしたいと思うのに、いつまでたってもちっともうまくできやしない。だから結局のところは、所詮中学生のクソガキだと思われてしかるべきなのだろう。
「それとも、部屋に男あげたら、こいびとが怒る?」
なんて、こんな風にませたふりをしても、いつだってダメージを受けるのは自分だけ。さんは一瞬きょとんとしてから、息をはきだすようにして笑った。
「まさか。たいせつな友達の可愛いおとうとくんに?」
そんなのわたしが怒らせないよ、と濡れた唇が渇いた笑いをうむ。
はじめてさんの家を訪れたときに見た、シューズラックに並ぶいくつかのルブタン。履いた彼女に見下ろされないようになれば、少しくらいは近づけると思っていた。でも、俺の背が伸びた分だけ、彼女だってどんどん大人になってゆく。見たことのない、けれど確実に気配のある、俺の知らない彼女の恋人。その存在がそうさせるのか、それともそもそも俺なんかには手の届かない存在なのか。会えば会うだけ彼女には隙がなくなって、この慣れ合いにはまったくもってほころびがない。
「でもまーくんは大人っぽいから、知らない人が見たらびっくりしちゃうかな」
俺がガキくさく拗ねたことを察してそんなことを言って見せる彼女は、その態度がいかに残酷かということにはちっとも気づかない。「ほんと、背もすごい伸びたよね」といって隣に立ち止まるのも、それを測るように俺の頭に手をかざすのも。その笑顔からは、今日出会い頭に見せてくれた、あの無防備さなどとうに消え去っていた。
「パンプス履いててももう見下ろせないね」
「……でも、差はちいとも埋まった気がせんよ」
いざこのひとを前にするとほとんどなくなってしまう、なけなしのプライドをむりくりに引っ張り出してきて。苦し紛れにそう言った俺の言葉が聞こえているのかいないのか、目の前で笑う彼女はどこまでもとおい。本当は、もう背伸びなんかしなくたって、その細い肩をむりやり抱き込んでしまうことも、その濡れた唇を力づくで塞いでしまうことも、いくらだってできるのだ。あたまのなかでは、何回だってそれをした。けれども、そんなくだらない戯れの妄想をいくつ重ねたところで、ふたりの関係の何が変わるわけもない。さんにとっての俺は、どこまでいっても友達の弟のチュウガクセーなのだ。
だからほんとうは、疲れるばかりのこんな恋は捨ててしまいたい。それでも、「いこっか」と笑って歩き出す彼女の背中を、少しの距離をあけてついていくことをやめられない。あなたがすきだと、どうしても言えない気持ちだけがただひたすらに積もってゆく。それを、我慢してがまんして、いつかあなたがその手でトドメをさしてくれるのを待っている。そんな男らしさのかけらもない情けない気持ちを慰めるように、彼女のうつくしいピンヒールが夜の冷えた空気を鳴らしていた。
いつまでも、あなたは俺の、残酷で、いとしいひと。