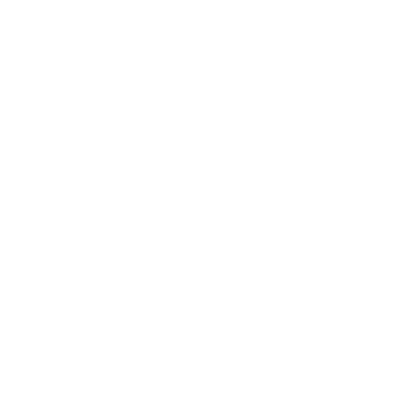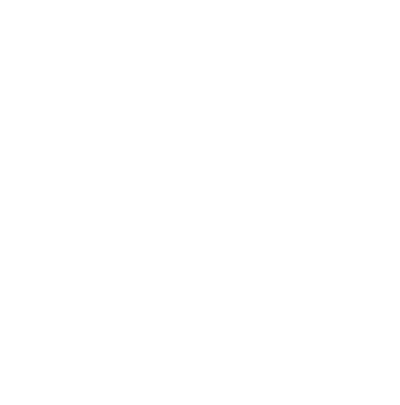
深夜二十三時半のコンビニエンスストアには、やる気のない大学生アルバイトのおにーさんと、仕事帰りの疲れたスーツのおねーさんと、ワンピースにパーカーを羽織りおろしたてのミュールを引掛けた十五歳のわたし。かわいらしい女の子たちが披露する色とりどりの冬コーデを流し見していたら、聞きなれたメロディーが流れて夜風が店内に舞い込んだ。嗅ぎなれた甘いにおいが鼻をくすぐる。
「おい」
これまた聞き慣れたちょっと怒った風の声に顔を上げると、眉間にシワを寄せた恋人の姿。高級そうなドレススーツに身を包み、ばっちりと髪を撫でつけた彼の姿は、煌々と店内を照らすコンビニの安っぽい光とあまりにもちぐはぐでちょっとだけ笑えた。高らかな音を立てて近づいてきた景吾はパシーンとわたしの頭を小突く。彼はいつだって加減を間違えることなんかなくて、ポーズばかり完璧なおいたは、ぜったいにわたしを痛めつけたりしない。
「家で待ってろって言っただろーが」
「だあってえ」
自由奔放な姉と兄の影響で両親が放任主義なのをいいことに、呑気にひとりで出かけた先から『近くのコンビニにいるね~』と一方的なメッセージを送ったわたしに彼はたいそうご立腹のようだ。「親御さんは?」と問うた彼はあまりにも不機嫌だった。まあまあ、こんなめでたい日にそんな顔しないの!と言ったら、今度は強烈におでこを弾かれる。ほらね、ちっとも痛くない。
「ったく、もういくぞ」
「あ、待って買う。先出てて」
ぐい、と引かれた腕をそっと解いて、小走りでスイーツのコーナーに向かえば、後ろから呆れたような溜息が聞こえたけれど、そんなのいつものことだからちっとも気になんかならない。カットされたショートケーキをひとつと、向かいの棚に並ぶドリンクの中からカフェオレを手に取ってレジへ向かう。近頃はコンビニのスイーツも侮れなくて、種類もたくさんあるし、下手するとその辺のケーキ屋さんよりおいしいことだってある。何より、こんな時間に買うことができるって特別だ。といっても、景吾はたぶん食べたことない(食べたいと思ったこともない)と思うけど。気怠げな店員さんからおつりを受け取って入口の方を見たら、前にお会計したスーツのおねーさんがドア横で腕を組んで立っている景吾のことを三度見していた。あのね、おねーさん。残念だけどそのひと、十五歳になりたての中学生なんです。
いつもよりさらに大人っぽい恋人の姿に、スキップしそうになる気持ちを抑えて隣に並び、自動ドアを抜けた。ちょっと間の抜けたメロディーも、スーツ姿の景吾の腕を掴んでくぐれば、今日だけは恋人たちのワルツに聞こえる。かもしれない。
「ね、景吾」
「あ?」
「かっこい」
立ち止まって腕を引いて、まるで内緒ばなしみたいに耳元に告げたら、景吾は小さく息を吐き出すようにして笑った。「バーカ」って言いながらポケットから手を出して、わたしの手を取って歩き出す。自分だけに向けられるこの笑顔の優しさとか、繋いだ手のあたたかさとか、そういう些細な幸福を、ずっとずっと忘れないでいたいな。
百メートル先に目をやれば、手入れの行き届いた黒のセダンがハザードをたいて停まっていた。
「疲れた?」
「別に。たいしたことじゃねぇ」
ご子息のバースデーパーティーという名の、大人たちの様々な思惑がうごめくビジネスの場。おろしたてのスーツとピカピカに磨かれたシューズを身に付け淡い髪を後ろへと流した彼の、露になったその端正な顔立ち。道端の外灯ですらそのうつくしさを確認するには十分なのに、パーティー会場の豪奢なライティングの下では、彼はどんなに輝いていただろう。いくら実質は大人たちの社交の場だからといったって、名目上の主役である彼が会の半ばで抜け出せるわけもなく、誕生日を一緒に過ごしたいというこいびとのわがままを叶えるためだけに、お開きと同時に着の身着のまま駆けつけてくれた。まさか、住宅街のコンビニに入店する羽目になろうとは夢にも思わなかっただろうけれど。
息を潜めるように停車する高級車の運転席がぎりぎり見えるか見えないかのところで、わたしたちは示し合わせたように足を止めた。ちゃんと確認なんてできないけれど、かたちだけでもと会釈したら、運転席の人影もなんとなく動いたような気がした。景吾はそれを遮るようにわたしの左側へとまわった。人通りのない道路のガードレールにふたり一緒に腰かけて、先ほど買ったばかりのコンビニの袋を広げる。こんなところを学校の先生みたいな大人に見つかったら大目玉をくらいそう。夜のガードレールにたむろする中学生のカップル。どう考えても不良みたいなのに、ひとりはばっちりキマったスーツ姿で、ひとりは季節外れの生足に華奢なミュール。いろんなことがしっちゃかめっちゃかで、なんだかおかしかった。
「お前それ寒くねぇのか」
「えー、かわいいでしょ?」
お姉ちゃんに買ってもらったんだー、といってミュールを引掛けた足をあげてみせたら、景吾はちょっと笑ってから「似合ってるじゃねぇか」と囁いた。てっきりいつもみたく、馬子にも衣装だとか、まあまあだとか、そんな軽口が飛んでくると思ってたのに。めずらしく素直な恋人の言葉に、心がぎゅっと締め付けられて、嬉しいような照れくさいような。やっぱりすごくうれしくて、なんだかちょっと泣きそうになった。それをごまかすようにごそごそとカフェオレを取り出して景吾に渡す。ちょっと持ってて、と言ったらなんだか少し不服そうにしていた。ポップなパッケージがやっぱりぜんぜん似合ってなくてちょっとおかしい。ショートケーキのパックを開けて、プラスチックのフォークで生クリームを大きく掬う。まず一口目は本日の主役、景吾くんにあげましょう。あーんと言ってフォークを差し出したら、素直に口を開けるので心底驚いた。もう一度掬って、わたしもひとくち食べてみる。あまい。おいしい。しあわせの味だな、と思った。
景吾は持っていたカフェオレにストローをさし、ごくりとひとくち飲み込んで呟いた。
「あめぇ」
「えぇ、おいしいじゃん」
お子様舌だなと景吾が笑うので、左肘で脇腹を小突いておいた。そんなこと言ってるといちごあげないよ?間髪入れずにどんどんケーキを掬うわたしを見て彼はまた、あのちょっと呆れたみたいな、甘やかすみたいな、とくべつ優しい恋人の顔をして笑った。「いーからお前食っとけ。好きなんだろ?いちご」だなんて、ほんとに今日はとことんわたしの心臓を脅かしてくるね。景吾のお祝いで買ったケーキだったのに、幸福になっているのはわたしばかりのような気がした。
「お前、つきまくってんぞ」
こっち向け、と言って彼はわたしの顎を掴んだ。右手の親指が少し乱暴に唇の端をぬぐう。あ、とこちらが言うよりも先に、彼はクリームのついた指をぺろりと舐めた。
「お行儀悪い」
「バーカ。どの口が言ってんだ」
最後の一口を放り込んだわたしの鼻をぎゅっとつまんで、軽く触れるだけのキスを落とす。ちょっとだけ乗り移ってしまった生クリームを舐めとった彼の色気といったら、とても十五歳なんかには見えなかった。甘いと呟いた景吾はまたひとくちカフェオレを飲んでから、今度はそれをわたしに差し出した。手を使わずに顔を寄せたら「横着すんな」なんて言ってきたけど、ちょっと意地悪な風で笑う顔がどこまでも優しくってほんと嫌になる。
彼がすきだ。たいせつだし、とくべつだ。絶対ぜったい、失いたくなんかない。訪れるかもしれないいつかを想像するだけで逃げ出してしまいそうになるわたしは、本当は、贅沢者だ。自分の誕生日だというのに彼は、今日中に会いたいと願ったわたしのために会いにきてくれた。お祝い気分を味わいたかったわたしのために口にあうはずのないバースデーケーキを食べてくれた。他の誰にも見せない顔で、笑ってくれた。たった一度しかない、十五歳のわたしたちの今日。スーツの袖口から覗く腕時計をみれば、針の隙間はどんどんなくなってゆく。
「誕生日、終わっちゃうね」
景吾は、向かい側からわたしたちを照らす外灯を見つめていた。秋の匂いのする冷たい風がわたしたちを撫ぜる。永遠だと思っていた夏が終わって、秋がきた。あの夏を超えて、変わってゆくことと、決して変わらないこと。その両方をわたしは、ひとつも逃さずにいたかった。
秒針は進む。景吾の向こう側で点滅するオレンジの光。
「、」
ゆっくりとこちらを振り向いてわたしの名前を呼ぶ声のあまさに、鼻の奥がツンとした。今日という日の終わりを隠すように遮って、誰からも、誰のことも、決して目に入らないように、景吾はわたしを引き寄せた。まるで存在を確かめているみたいに、景吾の掌がわたしの頬をやさしく包む。その温かい手の向こう側で、規則正しい音が響いている。泣いてなんかいないのに、涙を拭うみたいに親指が目の下を撫でた。宝石のように透き通るブルーの中で、わたしがこちらを見つめている。静かに瞼が下りて、彼はわたしを支配した。
「あいしてる」
景吾の声が耳に溶けて、染みてゆく。いまこの瞬間の幸福を信じて逃がさないために、この胸の苦しみがまぎれもない恋だと確かめるために、わたしたちはそっと唇を重ねた。耳元で鳴っていた針の音はもう聞こえない。おめでとうもあいしてるも飲み込んで、混ざりあってゆく温度だけが、わたしをいまここに生かしていた。