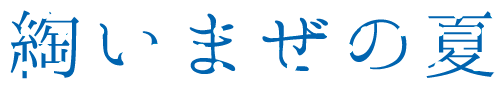
カラン、カラン。華奢なスプーンが不透明な白色を混ぜるのにあわせて氷が鳴った。ふたりでいるのに、グラスはひとつ。そんなことがとてつもなく幸福で可笑しくてちょっぴり、切ない。放課後、制服、彼の家。ああ、わたしはいままさにこのひとに恋をしているのだなあと胸をぎゅっと掴まれる。開け放った窓から風が吹き抜けて、わたしたちの火照った身体を撫ぜた。外は灼熱。降り注ぐ日射しの向こう側で、庭木がゆらゆら揺れていた。仁王は自分でつくったカルピスを一口。
あ、眉間に皺がよっていく。
「あっま」
「うそ、飲みたいのみたい」
わたしの好奇心に目を細めた彼から失敗のグラスを奪いとれば、「水足さんとだめじゃ」といって仁王はむりやり取り返そうとした。やめて、やめない。繰り返す攻防。じゃれあって絡んだ脚。不意に倒れそうになったわたしを後ろから抱きとめる、腕。その腕の力強さにこの身をあずける心地よさを、わたしはもう知ってしまった。少しだけ日に焼けたような気のする肌がいやに切なくて、ああ、今年も夏が来たのだなあと思い知らされるのだ。それはわたしの十五歳の恋心をそっと抉る。けれども、こんな気持ちは彼にはけっして覚られてはならない。
「なにふらついとんの」
「ごめん…」
「あ」
甘い、あまい、すっごくあまい。わたしを支えて覗き込んだ仁王の隙をみてゴクリ、と。仁王のつくった原液多めのカルピスが喉を伝って、身体の奥にしみ込んだ。あまい。あまったるくて、くせになる。「おいしいよ、わたしはすき」仁王は呆れた顔をして、抱きとめる腕に力を込めた。首筋を掠める、少し長めの髪先がくすぐったい。あ、似てる。半分透明の、白色だ。
「」
「な、に」
あ、キスされる。と思ったのに、折りてきたのは額だった。コツン、と音をたてて。いや、ゴツンって。「いうこときかんオシオキ」だなんて、こんなにくすぐったくて幸福なお仕置きがあってたまるもんか。眼前の琥珀色に映る自分をみて、そのあどけなさに驚いた。ねえ、あなたはどんどん大人になってゆくね。あの、ネットの貼られた白線の内側で。もとから大人っぽいあなただけど、もうわたしには到底追いつけそうもない。きっと、この夏もこえてあなたは———
口の中に残る白いざらつきは、あなたに恋する気持ちに似ている。喉につかえてしまって、なかなか飲み込めない。
「ね、カルピスのぎょろぎょろってさ、残る人と残らない人がいるんだって」
「なんで?」
「唾液の成分の違いだって」
「ほー」
スマートフォンから仕入れた受け売りの情報を受け流して、仁王はそっと冷蔵庫を開け、ミネラルウォーターを取り出した。グラスの中でふたつの液体がゆらゆらと揺れる。抱きしめられれば苦しいくせに、あっさり手放されてしまえばそれも苦しいのだから嫌になる。さっきまでわたしを抱きとめていた彼の指は、白くて、細くて、長くて、それでいてとても力強い。溜息の出るような指先を、もったいぶるように水滴が伝っていた。ペットボトルも、グラスも、あっという間に汗だく。そのくらい、暑い。今年の夏は、あついのだ。
仁王の手であっさりと薄められてしまったその白い飲み物のように、わたしのこの気持ちも簡単だったらどんなにいいのだろう。あなたがわたしへと向ける優しい眼差しも、あの黄色いボールを追いかける鋭い瞳も、おんなしだけ好きでいたはずなのに。いまはそんな気持ちも、ぐちゃぐちゃに絡まったコードみたいに解くことが難しい。
「仁王は残る?」
「いーや。残ったことなか」
キッチンからリビングへと移動するだけなのに、仁王はなぜかわたしの手をとる。
教室での彼はとてもそっけない。掴みどころのない仁王くん。テニス部のレギュラーで、明るく目立つ髪色で、ミステリアスで、女の子たちは密かに憧れを抱いてる。だからあの教室の中で、わたしにそっけなくする彼は、じつはとても優しい。そのかわりというように二人きりでいるときのわたしたちは、一秒でも長く、一ミリでも近く、触れて、まじわっていたかった。
そっとソファに腰掛けて手の中のグラスを傾ければ、喉仏がうごく。ひとくち、ふたくち飲んだあと突然、「ぎょろぎょろってなんじゃ」と呟いて仁王はくつくつと笑いだした。わたしの擬態語がなぜだか急にツボにはまってしまったらしく、規則的に肩を揺らして苦しそうだ。「ねえちょっとそんな笑う?」なんだか悔しくなって肩を小突いたけど、暖簾に腕押しヌカに釘。ちっともきいてない。
「わたしからしたら残らないほうが不思議だもん。ほんとになんもない?」
「んじゃ、確かめるか?」
ずい、と突然まじめな顔。ねえ、さっきまでの爆笑はどこにいったの?急に近づいた距離にわたしが怯んで後ろに下がれば、薄い唇がゆっくりと動いて釣り上がる口端。からかわれてる。ソファの背に預けた左腕が伸びてきて、手のひらが頭のてっぺんを撫でた。ぞくり、と身体の内側が疼く。こんな風に仁王の余裕に屈したくない幼いわたしのなかにも、きっと、少女らしからぬ気持ちが棲んでいる。あなたはそうやって、わたしのことを慈しもうとするけれど。
「まあま、これでも飲んで機嫌なおしんしゃい」
「べつにむくれてませんけど?」
「はいはい」
またひとつ彼は笑って、わたしの手に水の滴るグラスを握らせた。ぱたぱたと落ちた雫は、あっさりと白いシャツへと吸い込まれてゆく。向こうを見透かせない白色を見つめて、自分のすぐ右隣にある体温を想った。恋人になったはじめての夏、仁王雅治というひとが、あのコートの中で灼熱の太陽を受ける姿などとても想像できなかったはずなのに、いまでは強い日射しのなかで目を閉じるだけで瞼にうかんでしまう。まるで蜃気楼のように、けれど、いやにはっきりと。黄色いボールを打ち返す、彼のたくましい背中。汗が伝って輝き弾む、彼の透き通る髪。そうだ。彼の髪はあのコートの中で、一層うつくしく閃く。
彼が水を足し、氷が溶けて、薄まってしまったカルピスを飲み干せば、わたしの口の中にはざらりとした白い塊が残った。ほんとうに、彼には残らないのだろうか。あなたとわたしは、違ったもので出来てるの?
空っぽになったグラスをローテーブルに置いたら、仁王がこちらの顔を覗き込むようにして笑った。「残っとるか?」なんて、悪戯っ子みたいに聞いてくる。本当は、わたしのなかに残るもののこと、知ってほしい。わたしとあなたをかたちづくるものが、どんな風に違うのか、教えてほしい。
「確かめさせて、のくちんなか」
「まさは、る」
シャツ同士の擦れる音がして、彼の薄い唇がわたしに重なった。ゆっくりと確かめるみたく、お互いのなかをなぞりあえば、わたしたちの成分も混ざり合ってゆくような気がした。彼が注いだミネラルウォーターが、あの白い飲み物にあっけなく混ざっていったように。ゆらゆらと。
そうして、彼に溶かされてしまったのか、はたまた飲み込んでしまったのか、あのわずらわしい塊はいつのまにかわたしの中からなくなってしまっていた。もはや、何を確かめようとしていたのかも忘れてしまったように、次第に深くなってゆく口づけに、理屈も、意地も、すべてがすっかり溶けてゆく。
こうして彼の手がわたしの身体をソファへと縫いとめてゆくことのいとおしさ。ただそのことだけに、意識を集中させてゆく。
だからいまだけは、わたしたちが違うもので出来ていることなどは忘れて。ふたりを、いっしょくたにして。